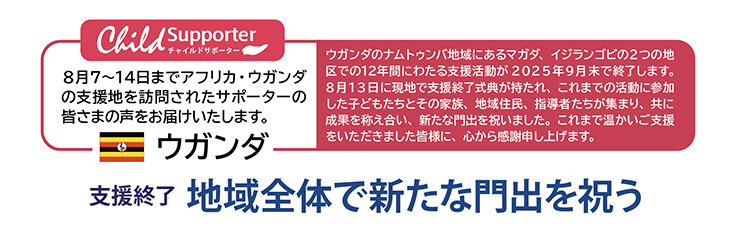

貧困から卒業する姿を実感
 支援が子どもの学用品だけではなく、彼らの家族、居住地域の支援にも充てられていることを知りました。例としてよく聞いたのが、先ずは一匹の山羊を買い、そこから頭数を増やして売却し、家計を満たし現金収益としていく。さらにコミュニティで貯蓄グループ、農業協同組合(農協)を組織するまでに拡大しているとのこと。自分たちが育てた農作物や家畜を誇らしげに我々に見せて下さる様子を目の当たりにし、地域が貧困から卒業するというのはこういう姿を指すのかと実感することができました。(家入聖子)
支援が子どもの学用品だけではなく、彼らの家族、居住地域の支援にも充てられていることを知りました。例としてよく聞いたのが、先ずは一匹の山羊を買い、そこから頭数を増やして売却し、家計を満たし現金収益としていく。さらにコミュニティで貯蓄グループ、農業協同組合(農協)を組織するまでに拡大しているとのこと。自分たちが育てた農作物や家畜を誇らしげに我々に見せて下さる様子を目の当たりにし、地域が貧困から卒業するというのはこういう姿を指すのかと実感することができました。(家入聖子)
■ ■
日本が衛生面、技術、インフラ等すべての面でどれだけ恵まれているかを実感しました。この技術を日々向上させながら、ほかの国も助ける。そういう国にしたいと思いました。(高校生 Y.K)
私たちは貧しくない
FHのスタッフがこの地域のために一番よく働いてくださっていることに気が付きました。どこの村に行っても村の人々がFHの方々を歓迎しているのを見て、しっかりと関係を築きながらサポートをしていることがすごいと思いました。(中学生 M.K)
■ ■
「人々の考え方を変える」。現地で何度も聞いた言葉ですが、決して簡単なことではありません。現地のディレクターが、「私たち(彼ら)は貧しくない、土地もあるし、働くことのできる手もある。私たちは貧しくない」と穏やかに、でも毅然と話す姿が忘れられません。人々の考え方は確かに変えられていました。種や家畜を支給され、今はご自分たちでそれを管理し増やし生計を立て子どもたちに教育を受けさせ、協力しながら奮闘しておられました。(H.K)
支援とは互いに励まし合うもの
数年間支援を続けてきたチャイルド、アネット。これまで写真や手紙を通してしか知らなかったアネットが目の前に立ち、笑顔で迎えてくれたとき、言葉にできない喜びが溢れました。現地では、FHスタッフやボランティアの方々がヤギや豚、牛などの家畜を援助し、貧困家庭が少しずつ自立していく姿を目の当たりにしました。支援とは一方的に与えるものではなく、互いに学び合い、励まし合うものなのだと実感しました。現地の方々の強さと優しさに触れ、私自身もまた多くの気づきと新たな視点をいただいたことを心から感謝しています。(N.K.)

弾けんばかりの笑顔のナムトゥンバのたくさんの子どもたち、下の子をずっとおんぶしている子、決して綺麗ではない服、裸足でも元気に走り回っている子...できるだけ多くの子どもたちに励ましの思いをこめて肩をポンポンして、ハイタッチして、一緒に笑いました。彼らの心に私たちの訪問と交流の時が刻まれて、彼らのこれからの世界に何らかのインパクトをもたらすこととなれば嬉しいです。(近藤千絵)
「世界は変わる」は本当だった
 現時点という横軸で見たら、「自分1人が1人を助けても世界は変わらない」。だけど、未来という縦軸で見たら、「自分が1人を助けて、その子が医者になったら、その子を通して助かる命がある。その子が先生になったら、その子を通して教育を受けられる子どもたちが出てくる。自分が支援をして教育を受けられたカレブ君の感謝が伝わる。父親も自分が支援したことで、牛を飼うことができ、その牛乳は家族(カレブ君は8人兄弟)の栄養となり、収入も得ることもできるようになり、彼の家族も変わった。「1人が1人を助ければ、世界は変わる」は本当だったのだ。その事実を今回、身をもって知ることができた。(最上裕恵)
現時点という横軸で見たら、「自分1人が1人を助けても世界は変わらない」。だけど、未来という縦軸で見たら、「自分が1人を助けて、その子が医者になったら、その子を通して助かる命がある。その子が先生になったら、その子を通して教育を受けられる子どもたちが出てくる。自分が支援をして教育を受けられたカレブ君の感謝が伝わる。父親も自分が支援したことで、牛を飼うことができ、その牛乳は家族(カレブ君は8人兄弟)の栄養となり、収入も得ることもできるようになり、彼の家族も変わった。「1人が1人を助ければ、世界は変わる」は本当だったのだ。その事実を今回、身をもって知ることができた。(最上裕恵)
ようやく支援チャイルドに会えた
 今回のハイライトは、やはりサポートを通じてやり取りしてきたチャイルドとの実際の対面である。当日は学校の試験があり、試験の合間にわざわざ戻って来てくれ、「ようやく会えた!」という喜びの思いが溢れ、握手をして抱き合った時は感無量だった。彼の叔父がFHを通じて行われた農業指導や教育資材の購入、牛の繁殖について語ってくれた。小さな働きでも、遠い国で誰かの人生を変える一助となる。今回の訪問でその事実を知れたことが、何よりの喜びであった。(福島雄樹)
今回のハイライトは、やはりサポートを通じてやり取りしてきたチャイルドとの実際の対面である。当日は学校の試験があり、試験の合間にわざわざ戻って来てくれ、「ようやく会えた!」という喜びの思いが溢れ、握手をして抱き合った時は感無量だった。彼の叔父がFHを通じて行われた農業指導や教育資材の購入、牛の繁殖について語ってくれた。小さな働きでも、遠い国で誰かの人生を変える一助となる。今回の訪問でその事実を知れたことが、何よりの喜びであった。(福島雄樹)
教科書の「貧困問題」がリアルに
 ウガンダの職業構成比を調べてみると、7割が農林漁業に従事し、次に多いのは2割を占める管理職だった。政府関係者とその他、といったように職業が二極化している印象を受けた。国際協力・開発学の授業で学んだ、「経済成長があっても、その恩恵が不均等に分配されれば貧困は残り続ける」という学説を思い出し、富がもっと公平に行き渡ればよいのにと思った。これまで教科書やメディアを通して得た「知識」にすぎなかった貧困の問題が、ウガンダでの経験を通じて現実味を帯びた。(大学生 北田綾子)
ウガンダの職業構成比を調べてみると、7割が農林漁業に従事し、次に多いのは2割を占める管理職だった。政府関係者とその他、といったように職業が二極化している印象を受けた。国際協力・開発学の授業で学んだ、「経済成長があっても、その恩恵が不均等に分配されれば貧困は残り続ける」という学説を思い出し、富がもっと公平に行き渡ればよいのにと思った。これまで教科書やメディアを通して得た「知識」にすぎなかった貧困の問題が、ウガンダでの経験を通じて現実味を帯びた。(大学生 北田綾子)
子どもたちを支える方法は2つ
特定の子どもとつながって成長を見守りたい!
そんな方は「子どもを支援する」
子どもを取り巻く環境の改善を応援したい!
そんな方は「活動を支援する」